車の永久抹消とは?手続き 知らないと失敗
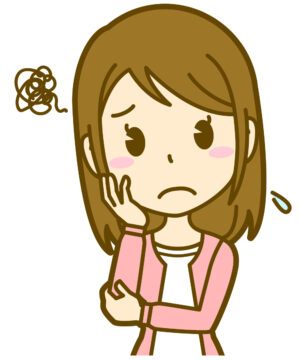
使っていない車があるから廃車にしたい。永久抹消の手続きってどんなことをすればいいの?
故障や年式が古い車を廃車にするときの、永久抹消の手続きについて説明します。
また自分で廃車手続きをするデメリットもあるので参考にしてください。
車の永久抹消とは?登録の流れ
永久抹消はその車に二度と乗らないことを意味する手続きです。
永久抹消登録を行う場所は、現住所を管轄している運輸支局にて行います。

登録されたままの車を放置していると、自動車税の課税対象になるので損をしてしまいます。
永久抹消の手続きをとることで、還付金の対象にもなるのでお金が戻ってきます。
車の永久抹消の流れ
一時抹消の流れは以下になります。
- 必要書類の準備
- 手続き費用の準備
- 管轄運輸支局で確認

手続きは結構面倒なので時間がない方は大変だと思います。
- 所有者の印鑑証明(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 所有者の実印が押された委任状(所有者本人が行う場合は不要)
- 車検証
- ナンバープレート(前後一枚ずつ)
- 「移動報告番号」「解体報告記録」が記載されたメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税/自動車税申告書(地域によっては不要)
永久抹消を自分で行う時は費用はかかりません。
廃車にするとお金がかかる
廃車にするために永久抹消をする場合、お金がけっこうかかるので注意してください。
- クルマを解体(解体業者に依頼)
- 必要な書類を揃える
- 管轄の運輸支局に行く
- ナンバープレートを返却
- 書類を提出
- 還付金手続きを行う

廃車をスクラップ業者などに依頼すると、それなりの金額がかかります。しかも還付金の手続きも面倒で凄く時間がかかりました。
| レッカー代 | 10,000~30,000円 |
| 解体費用 | 20,000~30,000円 |
| 手続き費用 | 10,000円~ |
もし廃車目的で永久抹消をするなら、廃車の買取業者に依頼するのがおすすめです。

無料で廃車手続きを全て行ってもらえる専門業者があります。しかも還付金の手続きも代行してもらえるので超簡単!
ネットで条件の良い廃車買取サービスがあるので共有しますね。
